「ゆきたん、きょう、なにちてあちょぶ?」
木実と小雪は4才。2人いっしょの生活にもすっかり慣れた。
乳母が作ってくれたお揃いのスモックは、木実が薄いブルーで小雪が薄いピンク。色の白い小雪にはピンクがよく似合う。
小雪は木実を見たまま、首をかしげた。一生懸命考えて、にっこりして言う。
「おちょと」
「おちょと、いく?わかった」
木実は小雪に手を差し出した。小雪は嬉しそうに木実と手をつなぎ、2人でとことこと庭に向かった。
季節は春。Σの殺風景な庭にも花がちらほら咲いていた。そよ風がそよそよと心地よく2人の頬を撫でる。
「ゆきたん、ちゃむくない?」
木実は幼いながらも、小雪の身を案じて言った。小雪はこの冬に風邪をこじらせ、10日以上も寝込んでいた。木実に比べ、小雪は抵抗力が弱く、風邪を引きやすい。辛くても、辛いと決して口にせず、おとなしくベッドで天井をみつめているのが健気だった。木実にしてみれば、風邪がうつるからと小雪に会わせてもらえなかったのが一番辛かった。毎日うろうろと部屋の前を行ったり来たりし、小雪が治った時は安心のあまりわぁわぁと泣いてしまった。
「へいき」
「いってね。」
「ん。」
こくんと頷くと、肩まで伸びた髪がゆらゆらと揺れた。日の光を浴びて、銀にきらきらと輝いている。
「ゆきたん、かみのけ、きれい」
木実は思わず小雪の髪に手を伸ばした。髪は細く透き通るようで、木実の指の間をさらさらと滑り落ちた。
「あいがと」
小雪はちょっと目を伏せてから、木実を見る。ためらいがちに木実の髪に触れ
「なっちゅも」
と恥ずかしそうに付け加える。
木陰にあるブランコに2人で座る。
しばらく2人で空を眺めたり、鳥の声に耳をすましたり。
時々顔を見合わせてにっこり笑う。
「ゆきたん、おちてあげゆ」
木実は小雪が座ったブランコの後ろに立ち、そっと背中を押した。2才の頃はあまり変わらなかった2人の体格は、ここ数ヶ月で段々差が出てきた。色々な国の混じった血が体に流れている木実は、特に欧米系の血が強いらしく、骨格ががっちりしてきた。対して小雪は相変わらず小柄で華奢だ。肌の色はますます白い。もっとも小雪の肌は陽に当ると火ぶくれになってしまいかねないので、夏でも長袖が手放せない。それに付き合って木実も夏でも長袖を着るクセがついてしまった。
「あいがと」
小雪は、背中に木実の手のひらの温かさを感じながら、頬や額に当る風の感触を楽しんだ。日に日に小雪の感覚は研ぎ澄まされて来ていた。最近は目を閉じていても、部屋から部屋へ移動できるし、いつも遊んでいる庭の中くらいなら歩き回れるようになった。
「今日も仲良しね」
通りかかった乳母が2人に声をかけた。
「ケンカしたことないわよね、2人とも」
「けんか?」
小雪が小首を傾げる。木実との間にいさかいが起きるなんて考えられない。そして、友達といえるのは木実くらいというこの環境では、けんかはありえない。
「おやつの時間よ。いちどお部屋に戻りなさい」
「おやちゅ、だって、ゆきたん」
木実はゆっくりとブランコの綱を持ち、揺れを止めた。
「とまゆまで、まってね」
「あい」
小雪は大人しく言葉に従い、じっとブランコが止まるのを待った。
「ほーんと紳士よね、ナッツくん。」
乳母は感心したように木実を見た。木実の小雪に対する扱いは、幼いながら紳士が淑女に行うそれだ。あの、最初に会った日から、それはずっと続いている。
「幸せね、小雪ちゃんは」
「んーん。」
木実は首を左右に振った。
「ぼくがたのちいの。ゆきたん、かわいいから」
「あらあら。」
乳母は微笑んだ。男の子同士なんだけどな、とちょっと思う。でもいいか、まだ子どもだし。
「そうねえ、たしかに、小雪ちゃんかわいいものねえ。きっと美人さんになるわよ」
「うん」
木実は力強く首を縦に振った。
「あのね、けっこん、ちゅるの」
「え?結婚?ナッツくんと小雪ちゃんが?」
「ん。ね、ゆきたん」
「あい」
小雪は恥ずかしそうに頷いた。
「んー、それはどうかなあ」
乳母は少し不安になった。
「結婚できるといいけどねえ」
「…れきないの?」
乳母を見上げる木実の目が、びっくりしたように丸くなり、見る間に涙が溢れてきた。
「で…できないとは、言わないけど」
「ぼ…ぼく、ゆきたんいがいのおよめしゃんなんて、いやない。ゆきたんがいい」
ぼろぼろと涙がこぼれ、乳母は困ってしまった。
どちらかと言うと2人とも聞き分けはよく、めったにだだをこねることもない。木実はここに来たばかりの時は、家を恋しがってよく泣いていたが、小雪が来てからはすっかり落ち着いていた。
「なっちゅ」
小雪がブランコをぽんと降り、真後ろに立っていた木実に向き合うように立った。じっと木実の顔を覗き込み、頬に伝う涙に手を伸ばした。
「ないちゃ、や」
涙を自分の小さな手のひらで拭い、木実の頭をなでる。
「いいこ、なっちゅ」
「ゆきたん、ゆきたんは?ぼくとけっこんちたいよね、ね」
必死の木実の問いかけに、小雪は
「ん」
と頷く。
「よかった」
木実はほっと胸を撫で下ろし、照れ笑いをした。
「ごめんね。ゆきたん」
涙をちゃんと拭いてやろうと乳母が出したハンカチは払いのける。
「ゆきたん、ふいてくえたから、いい」
せっかく涙を拭ってくれた小雪の手のひらの感触を、忘れたくなかった。
「いこ」
と、また手をつなぐ。
「ん」
2人はまた仲良く部屋に戻って行った。
乳母は2人の後姿を見ながらため息を付いてしまうのを止められなかった。確かに仲がいい。でも、ちょっと仲良しすぎるのではないだろうか。『ペア』は単なるお友達ではない。相手が辛い仕事に耐えるのを目の当たりにしなければならない事もある。小雪はともかく、木実にそれが耐えられるのだろうか。思い悩みながら、2人の後について、部屋に入って行った。
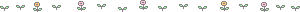
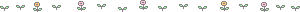
おやつのプリンを食べ終わると、外は陽射しが強くなり、遊べる状態ではなくなっていた。 「外出ないほうがいいわね。小雪ちゃんがまたイタイイタイになっちゃうから」 「うん、わかった。おうちいる」 木実は素直に頷いた。 「夕方になったらまた外で遊べるからね」 そういい残して乳母は食器を下げに部屋を出て行った。部屋の中には木実と小雪2人だけになった。 「ごほん、よむ?」 木実の言葉に、小雪はすぐに一冊の絵本を持って来た。 『白雪姫』。自分と同じ『雪』という字を名前に持つ女の子のお話が、小雪はとても気に入っていた。 「よんであげゆ?」 小雪は黙って嬉しそうに頷き、本を木実に渡した。 木実は言語能力がかなり高く、まだ舌もよく回らない内から文字を言葉として捉え、読むことができた。誰が教えたわけでもないのに、いつの間にか本を小雪に読み聞かせている木実を、まわりは奇異の目で見たが。 小雪は木実の隣にちょこんと座り、深紅の瞳をきらきらと輝かせ、熱心に絵本を見つめた。 「おきちゃきちゃまは、かがみにききまちた」 何度も見ているので、もちろん全部の文は小雪の頭に入っている。でも木実の声で読んでもらうのが好きだった。 「めちちゅかいは、ちらゆきちめを、おきじゃりにちまちた」 いつも白雪姫が森に捨てられる下りになると、小雪は悲しそうな顔になる。だからついそこの部分は早くなってしまう。多分、ここに捨てられた自分と似ているからと木実は思っていた。 「ちょこにいたのは、しちにんの、こびとたんでちた」 小人達が現れる場面では、いつも目を輝かせる。だからそこは、木実もゆっくり読む。 「おばあしゃんは、りんごをさしだちまちた」 白雪姫が毒りんごを食べるシーンでは、いつも息を詰め、木実の腕をぎゅっと両手で掴む。 「ちらゆきちめは、たおれてちまいまちた」 白雪姫が倒れる所では、自分も倒れてしまいそうなほど不安な表情になる。そこでいつも 「ゆきたん、だいじょぶ。おうじしゃまが、たちゅけにきてくれるから」 「あい」 という会話を交わすのが常だった。 王子が白雪姫を助けに現れ、結婚式のシーンでこの絵本は終わっている。 最後にいつも小雪はほーーーっと長いため息をつき、にっこりと笑って木実に 「あいがと」 とお礼を言う。 時によっては 「も、いっかい」 と言う時もあった。よっぽどこの本が気に入っているんだろうなと木実は思っていた。 何度も読んで、本はすっかり擦り切れてしまっていたが、それもまた2人の思い出のうちだ。 読み終わると、小雪は大切そうに絵本を窓際の本棚に戻した。満足そうな笑みを浮かべ、木実の方を振り返る。 その時、半分開いた窓から、風が吹き込んできた。 レースのカーテンが舞い、小雪の頭にふわりとかぶさった。木実は思わずその光景に見とれてしまった。 「ゆきたん、およめしゃんみたい」 小雪は恥ずかしそうにうつむいた。でも、木実が嬉しそうにしているので、頭の上のカーテンを払いのける事はできない。木実は立ち上がって小雪の傍に立ち、惚れ惚れとその姿を眺めた。 「およめしゃんは、おはな、もちゅんだよね」 「ん」 あたりを見回して花束の代わりになりそうな物を探す。 ちょうどそこに落ちていたきれいなスカーフを、おぼつかない手つきでくるくるとまるめ、小雪に持たせた。スカーフは先が広がり、まるで小花が咲き乱れる花束のようになった。 「え、と、ちょえでぇ」 木実は白雪姫の最後のページを思い出しながら言った。 「ぼくちしゃんが、いうんだよね。やめゆときも、ちゅこやかなゆときも」 「ん」 「とわに、あいちゅることを、ちかいまちゅかって」 「あい」 こくんと頷いて答える小雪を、木実はまぶしそうに見た。 「ゆきたん、それ、おへんじ?」 「ん?」 小雪は小首をちょこんと傾げ、ちょっと考えて、またにっこり笑って 「あい」 と答えた。 「ゆきたん、ぼくも。ぼくもきいて」 「ちかいまちゅか?」 「あい」 2人はしばらくじっと見つめあった。まるで本当に永遠を誓い合ったように、2人の胸はなんとも言えない温かい気持ちでいっぱいになった。『感動』なんて言葉はまだ知らなかったけれど。 しばらくして木実は口を開いた。 「そえで…およめしゃんに、ちかいのきちゅを、ちゅるんだよね」 「ん」 小雪は目を閉じた。木実が小雪の頬に、ちゅと音を立ててキスをひとつした。 「ゆきたん、だいちゅき」 小雪はゆっくり目を開き、真剣な顔で木実を見た。 「なっちゅ、だいちゅき」 2人は手を取り合った。そよかぜが2人を祝福するように通り過ぎて行った。
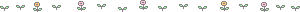
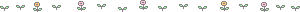
しばらくして部屋に戻って来た乳母は、2人の様子を見て、微笑んだ。 2人は手と手を握り合ったまま、ベッドで並んで眠っていた。 小雪の手にはまだしっかりとスカーフが握られている。 『ほんとうに仲良しさん』 そう呟いて、ふと表情を曇らせた。一年後に始まるであろう、辛く苦しい訓練を思って。 『でも、それまでは…、いえなるべく長く、今のままで…』 乳母はぐっすり眠っている2人にそっと掛け布団をかけ、静かにドアを閉めた。
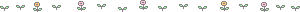
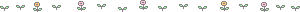
おやつのプリンを食べ終わると、外は陽射しが強くなり、遊べる状態ではなくなっていた。 「外出ないほうがいいわね。小雪ちゃんがまたイタイイタイになっちゃうから」 「うん、わかった。おうちいる」 木実は素直に頷いた。 「夕方になったらまた外で遊べるからね」 そういい残して乳母は食器を下げに部屋を出て行った。部屋の中には木実と小雪2人だけになった。 「ごほん、よむ?」 木実の言葉に、小雪はすぐに一冊の絵本を持って来た。 『白雪姫』。自分と同じ『雪』という字を名前に持つ女の子のお話が、小雪はとても気に入っていた。 「よんであげゆ?」 小雪は黙って嬉しそうに頷き、本を木実に渡した。 木実は言語能力がかなり高く、まだ舌もよく回らない内から文字を言葉として捉え、読むことができた。誰が教えたわけでもないのに、いつの間にか本を小雪に読み聞かせている木実を、まわりは奇異の目で見たが。 小雪は木実の隣にちょこんと座り、深紅の瞳をきらきらと輝かせ、熱心に絵本を見つめた。 「おきちゃきちゃまは、かがみにききまちた」 何度も見ているので、もちろん全部の文は小雪の頭に入っている。でも木実の声で読んでもらうのが好きだった。 「めちちゅかいは、ちらゆきちめを、おきじゃりにちまちた」 いつも白雪姫が森に捨てられる下りになると、小雪は悲しそうな顔になる。だからついそこの部分は早くなってしまう。多分、ここに捨てられた自分と似ているからと木実は思っていた。 「ちょこにいたのは、しちにんの、こびとたんでちた」 小人達が現れる場面では、いつも目を輝かせる。だからそこは、木実もゆっくり読む。 「おばあしゃんは、りんごをさしだちまちた」 白雪姫が毒りんごを食べるシーンでは、いつも息を詰め、木実の腕をぎゅっと両手で掴む。 「ちらゆきちめは、たおれてちまいまちた」 白雪姫が倒れる所では、自分も倒れてしまいそうなほど不安な表情になる。そこでいつも 「ゆきたん、だいじょぶ。おうじしゃまが、たちゅけにきてくれるから」 「あい」 という会話を交わすのが常だった。 王子が白雪姫を助けに現れ、結婚式のシーンでこの絵本は終わっている。 最後にいつも小雪はほーーーっと長いため息をつき、にっこりと笑って木実に 「あいがと」 とお礼を言う。 時によっては 「も、いっかい」 と言う時もあった。よっぽどこの本が気に入っているんだろうなと木実は思っていた。 何度も読んで、本はすっかり擦り切れてしまっていたが、それもまた2人の思い出のうちだ。 読み終わると、小雪は大切そうに絵本を窓際の本棚に戻した。満足そうな笑みを浮かべ、木実の方を振り返る。 その時、半分開いた窓から、風が吹き込んできた。 レースのカーテンが舞い、小雪の頭にふわりとかぶさった。木実は思わずその光景に見とれてしまった。 「ゆきたん、およめしゃんみたい」 小雪は恥ずかしそうにうつむいた。でも、木実が嬉しそうにしているので、頭の上のカーテンを払いのける事はできない。木実は立ち上がって小雪の傍に立ち、惚れ惚れとその姿を眺めた。 「およめしゃんは、おはな、もちゅんだよね」 「ん」 あたりを見回して花束の代わりになりそうな物を探す。 ちょうどそこに落ちていたきれいなスカーフを、おぼつかない手つきでくるくるとまるめ、小雪に持たせた。スカーフは先が広がり、まるで小花が咲き乱れる花束のようになった。 「え、と、ちょえでぇ」 木実は白雪姫の最後のページを思い出しながら言った。 「ぼくちしゃんが、いうんだよね。やめゆときも、ちゅこやかなゆときも」 「ん」 「とわに、あいちゅることを、ちかいまちゅかって」 「あい」 こくんと頷いて答える小雪を、木実はまぶしそうに見た。 「ゆきたん、それ、おへんじ?」 「ん?」 小雪は小首をちょこんと傾げ、ちょっと考えて、またにっこり笑って 「あい」 と答えた。 「ゆきたん、ぼくも。ぼくもきいて」 「ちかいまちゅか?」 「あい」 2人はしばらくじっと見つめあった。まるで本当に永遠を誓い合ったように、2人の胸はなんとも言えない温かい気持ちでいっぱいになった。『感動』なんて言葉はまだ知らなかったけれど。 しばらくして木実は口を開いた。 「そえで…およめしゃんに、ちかいのきちゅを、ちゅるんだよね」 「ん」 小雪は目を閉じた。木実が小雪の頬に、ちゅと音を立ててキスをひとつした。 「ゆきたん、だいちゅき」 小雪はゆっくり目を開き、真剣な顔で木実を見た。 「なっちゅ、だいちゅき」 2人は手を取り合った。そよかぜが2人を祝福するように通り過ぎて行った。
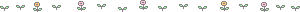
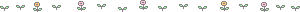
しばらくして部屋に戻って来た乳母は、2人の様子を見て、微笑んだ。 2人は手と手を握り合ったまま、ベッドで並んで眠っていた。 小雪の手にはまだしっかりとスカーフが握られている。 『ほんとうに仲良しさん』 そう呟いて、ふと表情を曇らせた。一年後に始まるであろう、辛く苦しい訓練を思って。 『でも、それまでは…、いえなるべく長く、今のままで…』 乳母はぐっすり眠っている2人にそっと掛け布団をかけ、静かにドアを閉めた。