小雪と木実が出会って1年とちょっとが過ぎた。二人でいる事にもすっかり慣れ、いつもいっしょの二人を回りは微笑ましく見守っていた。
ある夏の夜、いつも二人の面倒を見てくれる保母が、出かけることになってしまった。
夕食を済ませ、お風呂にいっしょに入れ、寝巻きに着替えさせてからも、彼女はまだ不安だった。
「大丈夫かしら。お留守番できる?」
「うん」
木実は健気に頷いた。でもちょっと不安だ。
確かにいつも部屋では二人だけで眠りに付く。しかし夜中に何度も彼女が様子を見に来てくれているのを二人とも知っている。怖い夢を見たり、どうしても眠れない夜は、いっしょに寝てもらうことも、ここだけの話だけど、ある。なんと言っても、二人ともまだ3才なのだ。
「だいじょぶ、ね、ゆきたん」
「ん」
小雪も小さく頷く。片手では木実の服の裾をぎゅっと握っている。
「明日の朝には戻れると思うの。お土産買ってくるからね、何がいい?」
「ん…と、ん…と」
木実は一生懸命考えた。
絵本はたくさんあるし、お菓子も毎日食べているから特にそれ以上欲しいとも思わない。テレビなどの情報もないので、玩具も何があるのかよくわからない。第一、小雪と二人でいっしょにいられればそれだけで幸せで、他に何か欲しいとは思えない。困って小雪に助けを求める。
「ゆきたん、なんかほちい?」
小雪も黙って首を左右に振る。
小雪はそれ以上に満ち足りていた。殆どずっと一人でいた頃に比べると、今の生活はなんて素晴らしいんだろう。いつでも木実がいっしょにいてくれて、自分が上手く言えない事や、伝えられない気持ちを何でも分かってくれて、いっしょに笑ったり泣いたりしてくれる。これ以上何も欲しいものなんてない。小雪はいつも木実に感謝の気持ちでいっぱいだった。
木実は小雪も同じ気持ちでいてくれるのがわかり、嬉しかった。
二人で顔を見合わせ、にっこりする。
「だって。おみやげいやない」
そう言ってから、『おみやげ』をちゃんと決められなくて、困らせたかなと思い、ちょっと不安そうな顔になる。
保母は二人を代わる代わる見比べ、体をかがめたかと思うとぎゅっと抱き締めた。
「本当に良い子」
「そうなの?」
木実は驚いて保母さんの顔を見た。
聞かれたことにちゃんと返事ができなかったのに、どうして誉められるんだろう?
「そうよ。こんなに…ううん、なんでもないわ。ごめんね。じゃあ、珍しいお菓子でもあったら買って来てあげる」
「うん。めずらちーおかち」
繰り返しながら、木実は『珍しいお菓子』ってどんなだろうと考えていた。この前作ってもらった2色のゼリーは珍しかったな。だって上がむらさきでぶどうの味がするのに、下は赤くていちごの味がしたんだ。すごく不思議だった。あ、それから前に食べた『かーりだま』って飴も不思議だった。だって舐めてると色が変わるんだ。それも何回も。あんまり不思議だったから、何度も口から出して眺めたっけ。
「ね、ゆきたん。たのしみだね、めずらちーおかち」
「あい」
小雪はカボチャの味のするプリンの事を考えていた。保母は食の細い小雪を心配して、なるべくおやつも栄養のあるものを美味しく食べられるように工夫してくれていた。見た目は普通のプリンと余り変わらないのに、食べたらカボチャの味がした。びっくりしてスプーンをくわえたまま保母を見たら、にこにこしていたっけ。それからなんだっけ、ふわふわして雲みたいなのに、口に入れると甘くとけて夢みたいな気持ちになるおかし。『わたーめ』?
素直に木実の言葉に従って頷く小雪を保母は複雑な気持ちで見た。
この、心優しく、物静かな子が、本当に一流のアサッシンに育つのだろうか?チーフは彼の持つ素質は間違いないと言う。確かに手先は今まで見てきた子達の中でずば抜けて器用だ。目を閉じたまま積み木で左右対称の立派なお城を作り上げたのを見た時は、仰天したものだ。しかし体はあまり丈夫でない上に、恐ろしく控えめだ。
それにこのお互いを気遣う心がかえって仇になったりしないだろうか。『ペア』は時に相手を犠牲にしなくてはいけない事態も起こりうるのだから。
しかし、それは自分が心配することではない。
自分の仕事はこの子達を訓練の始まる5才まで健やかに育て上げることだ。いくら自分が愛着を持ってもそこでどうせ引き離されてしまう。あまり踏み込み過ぎないように、心を鬼にするのも大切だ。
「わかった。楽しみにしていてね」
「うん。ゆきたんはぼくがちゃんとまもってあげゆ」
「頼もしいわね」
そういい残して彼女は部屋を出た。
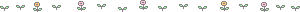
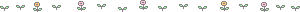
「ゆきたん、もうねる?ごほんよむ?」 時計は7時。まだ寝るのには早い。 「ごほん」 小雪は嬉しそうに答える。 二人は手を繋いで窓際の本棚に向かった。 「これ」 小雪は『ヘンゼルとグレーテル』の絵本を取り出した。最近『白雪姫』の次に気に入っている。 こどもが力を合わせて、大人や悪い魔女に立ち向かうところが好きらしい。 窓辺のクッションに腰を下ろし、二人並んだ膝の上に絵本を開いて木実が読み始めようとした、正にその時だった。 いきなり頭の真上で雷が鳴り響き、部屋の電気が消えた。 「わ…ああああ」 木実は驚いて、絵本を取り落とした。それでも小雪を守らなくてはという一身で両手をぎゅと握る。 「か…かみなりだ…」 「ん」 小雪は手を握り返した。 実はさっきから何か妙な予感めいたものを感じていた。でもそれが何かはわからなかった。今ならば小雪が感じていたのは微妙な気圧の変化で、それは雨と雷の予兆だと説明することができるのだけど。 「ゆ…ゆ…ゆきたん、だいじょおぶだからね。ぼ…ぼくがちゅいてるからね…」 「ん」 真っ暗闇の中で、小雪はこくりと頷いた。 停電に続き、雨がざあざあと音を立てて落ちてきた。それはあたりの音全てをかき消し、まるで世界中に自分達だけしかいないような不安感を煽り立てた。 でも小雪は平気だった。 だって木実がいてくれる。ちゃんと傍にいて手を握っていてくれるから。 もう一度大きな音がして、稲光が部屋を照らした。一瞬目が眩むばかりに部屋が明るくなり、木実は目を閉じてしまったが、小雪はいつもと違う部屋の様子をしっかりと見届けた。 きれいだ、と思った。 いつもよりも濃くなった陰影の中に、家具や出しっぱなしの玩具や木実の顔がくっきりと鮮やかに浮かび上がる。小雪はその光景を頭に刻み付けた。20年の年月を経ても、その時の様子はまるで一枚の絵のように、小雪の記憶にはっきりと残っている。一番古いいくつかの記憶のうちの一つとして。 「なっちゅ?」 黙ってしまった木実にそっと話しかける。 「へーき?」 「う…うん。こ…こわくないよ」 本当は…怖い。 雷なんてどうして鳴るんだろう。空の上で誰かが怒っているとしか思えない。どうしてあんなに怒るんだろう。自分に対して怒っているんだろうか?なんか悪い事をしただろうか。それで大きな音を出して怒りながら罰を与えにくるんだろうか?あんな大きな音を出すんだから、きっとすごく大きくて怖いものに違いない。 そうだ、ゆうべ、寝なさいと言われたのに寝られなくて、遅くまでお喋りをしていたのが分かったんだろうか? それともこの間、食べきれなくてゆきちゃんのの残しかけたお昼ご飯を食べてあげたのがばれたんだろうか? もしかして、お風呂の中でこっそり二人でお湯に潜ってみたのを誰かが見ていたんだろうか? そうだったらどうしよう。罰を受けるのは自分だけではすまないはずだ。 「ゆきたん、ぼくがまもってあげゆからね。ぜったいね」 「ん。あいがと」 「だからゆきたんもこわくないからね」 「ん。こわくない」 「よかった」 小雪のいつもと変わらない落ち着いた声にほっと胸を撫で下ろす。 そうだ、自分はどうなっても、一生懸命謝ってゆきちゃんは許してもらおう。ゆうべ寝られなかったのは自分で、ゆきちゃんは付き合ってくれただけだし、お湯に潜ってみようと言ったのも自分だったし。ゆきちゃんははすごく長く潜れて、ちょっと心配したっけそう言えば。やっぱりゆきちゃんってすごい。 そう思ってほおーっと大きなため息を付いたのと同時にまた大きな雷が鳴った。 「ゆ…ゆきたんっ」 「ん」 二人でぎゅっと抱き合って稲光と雷鳴をやり過ごす。ガラスまでもかたかたと震動するほどの大音響に、思わず身が縮む。 「くらいね」 小雪は部屋の隅に懐中電灯が置いてあるのを思い出した。何かあったら使いなさいと言われた時は、『何か』って何だろうと思ったけれど、きっと今が『何か』に違いない。 「でんき、ある」 「ど…どこに?」 「あっち」 小雪は暗闇の中で、部屋の隅を指差した。 「みえないよ、ゆきたん。みえゆ?」 「ううん」 正確に言えば『見える』わけではない。 でも小雪には暗い中でも物の存在を感じ取れる能力が備わっていた。 「わかゆ」 「わかんの?じゃでんきちゅけられんの?」 「ん」 小雪は立ち上がって懐中電灯をとりに行こうとした。 「まって。いっちょにいく」 木実は手をぎゅっと握りなおし、いっしょに立ち上がった。一人で取り残されたくない、それよりも暗闇に小雪が飲み込まれてしまいそうで不安だった。 どうして他の人が暗闇を気にするのか、小雪にはよく分からなかった。確かにものの形が明確に見えるわけではないので、明るい時と同じに動けるわけではないが。どうも自分以外は、暗闇では物の位置が殆ど分からないらしいと気が付いたのはごくごく最近の事だ。 暗くて歩くのも不安そうな木実を気遣って、ゆっくりと歩く。何分もかけて部屋を横断し、手にした懐中電灯を木実に渡した。木実は渡された小振りの懐中電灯のスイッチを入れた。柔らかい赤っぽい光が二人の回りを照らし、木実はほっと安堵のため息を洩らした。 「よかった」 そう言ってから照れ臭そうに付け加える。 「ごめんね。あいがとね、ゆきたん」 自分が守ってあげるといったのに、助けられてしまった。 ちょっと恥ずかしいけど自分は暗くても困らない小雪が、自分のために灯りのことを思い出してくれたのがうれしい。 木実は片手で懐中電灯を手に持ち、片手で小雪の手を握って慎重にまた窓辺に戻った。まだ雷はひどくて雨も強いけれど、少し明るくなったことで随分気持ちも落ち着いた。 でも、雷が自分達を怒りに来るかもしれないという不安はまだ消えない。 お星様にお願いしようとしても、今夜は全然出ていない。 二人で並んで空を見上げながら 「なんでかな?」 木実が呟いた。 「?」 小雪が不思議そうに木実を見た。 「かみなりなんでかな。なんでなるのかな?なんでぴかぴかするのかな?」 小雪はじっと考えた。 わからない。 自分は雷は怖くない。でもみんなは怖がっているみたいだ。どうして怖いんだろう。いつもはないほどの大きな音と光が出るからだろう。誰があんな事をしているんだろう。誰かが空でしているんだったら、それはとてつもなく大きな力を持った人間が太刀打ちできないような存在に違いない。それにその人がいつまでもそうしたがったら、雷もいつまでも止まらなくて、そうしたら大好きなお散歩もぶらんこもできなくなってしまう。 そんなことを漠然と思う。もちろんちゃんと言葉にしてそんなことを考えたわけではない。ただ、それが不安で不思議に思った。それを知るにはどうしたらいいだろう。そうだ。 「ほん」 「ほん?」 「でてゆ?」 「どっかな?」 木実はいっしょうけんめい考えた。 確かに本は役に立つ。本を見ると字も覚えて、それでまた新しい本が読めるようになる。 「さがす?」 「ん」 それだけしか言わないのに、自分が何をいいたいのかわかってくれる木実をすごいと思う。 他の人は小雪の言いたい事をほとんど分かってくれない。もっとちゃんとお話しなさいと言われるのもしばしばだ。木実だけは一言喋れば言いたい事を理解してくれる。 二人は窓辺の本棚を端から一冊一冊探して行った。 『しらゆきひめ』『あかずきんちゃん』『ももたろう』この辺は明らかに違う気がする。 『おるすばん』『はいきんぐ』これも違う。 『どうぶつえん』『すいぞくかん』ちょっと近づいてきたかな。 『ちきゅうのれきし』『みんなのかがく』あ、この辺かな? 木実は『みんなのかがく』を取り上げた。小雪に懐中電灯を渡して手元を照らしてもらい、ページを繰る。 「わかんないや」 がっかりして本を本棚に戻す。小雪も残念そうにそれを見守った。 「もう、ほん、ないね」 小雪は少し考えてから、ぱっと顔を明るくして言った。 「とちょしちゅ」 「え?とちょしちゅ?」 もっと一般的な本がまとめておいてある通称『図書室』は確かに存在する。しかしそこにはこども二人で行ってはいけないと言われていた。その上、夜なのに暗い廊下を通ってあんな建物の一番奥の方まで行くなんて。二人にとっては立派な冒険だ。 しかし懐中電灯に照らされた小雪の目は真剣で、木実は止めようとは言えなくなってしまった。いつも控えめな小雪だけど、一度言い出すときかなくなる事がある。 「わかった」 木実は頷いた。 「いこ」 「あい」 小雪は嬉しそうに言って立ち上がる。 懐中電灯は木実が持って、しっかりと手を繋ぎなおし、二人は部屋を出た。
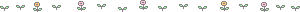
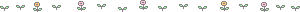
暗い廊下はどこまでも続いているみたいで、木実はおもわずごくりと生唾を飲み込んだ。小雪の手を自分を励ますようにぎゅっと握り、一歩一歩足を進める。 やがてたどりついた図書館も、当然ながら真っ暗だった。 「えと、えと…。どこいく?」 「こども」 「こどものほんのとこ?ん、わかった」 何度かしか来た事はないが、木実はどの辺にどんな本があるかは大体覚えていた。それは木実の能力だった。彼は一度会った人は忘れないし、一度行った場所は決して忘れない。 「このへんだよ」 「そら」 「そらのほん?ん」 木実は端から空に関する本を探し始めた。 『空』という字は知っていた。なぜ『そら』と『空』どっちもあるのかは分からないは。そのどちらもが自分達の頭の上に広がっている青かったり白かったり黒かったりするあの大きなものを指している事は、わかっている。 「これ?」 その中から、『そらのふしぎ』という本を探し出す。表紙にはキレイな青空が広がっている。内容は小学校高学年用のようだった。それを持って二人でテーブルにつく。 小雪は黙ってもくじを見た。 「かみなり」 「かみなり。これだね」 木実は『かみなりの秘密』という文字を探し出した。 「ええと。7と8のぺえじ?」 「7と8のぺえじ」 小雪が繰り返す。 二人は78ページに向けて1ページ1ページ、ページを繰っていった。 書いてある数字のところを見ると、その内容が書いてある事を保母から教わった。保母は二人が理解するか半信半疑だったが、木実は自分のやり方で理解したようだった。つまり数の成り立ちはわからなくて、78ページと26ページのどっちが先かは分からないが、同じ数のところにはとにかくそれが書いてあるというふうに。 「ここ」 「ん。ここ」 二人が見つけ出したページには、今空を走っているのとそっくり同じ稲光の写真が載っていた。顔を見合わせてにっこり笑い、木実はゆっくりと字を追い始めた。 「ん…と…むかちはかみなりを、くもの中にいるかみちゃまや、まものがあばれているものだとおもっていまちた。かがくがはったちゅするにちゅれ、かみなりは、あめがふったり、かぜがふいいたりするのと同じしぜんげんしょうであることがわかってきまちた…。だれかがやってるんじゃないんだ!」 木実はびっくりして小雪を見た。小雪も驚いた顔をしている。 「ぢめんやかいめんちかくのくーきがが、あたたまるとうえにあがります。ちゅるとおんどがちゃがり、ちいちゃいみじゅのちゅぶになります。これがくもでちゅ…くもってみじゅなのっ!?」 「ね」 小雪もますます驚いた表情になる。 という事は、あの不思議な雲みたいなお菓子も水なんだろうか? 「ね。え…と…ちゃらにうえにあがるとおんどがちゃがってこおりのちゅぶになります。それがぶちゅかりあってプラスのでんきがおきまちゅ…。ふう…ゆきたんわかゆ?」 「んーん」 さすがにところどころしかわからない。小雪は素直に首を振った。 ぷらすの電気ってなんだろう??電気って明るくて光ってるのだけじゃないんだ。 「ぼくも。でもよむね。…おもくて、ちたへおちていったこおりはマイナチュのでんきをおこちまちゅ。そのあいだのでんあちゅのちゃが大きくなると、ちょのあいだでほうでんしまちゅ。それがかみなりでちゅ…だって!」 やっとかみなりという言葉が出て来て、木実は良かったとにっこりした。 このままわけの分からない文を読んでいるのはさすがに苦痛だ。 「いなじゅまは、ほうでんげんちょうのひばな、らくらいはほうでんでちゅ。くもと、ちじょうのあいだを、なんどもほうでんをくりかえちてちじょうにちゅきます。しかしにんげんにははやちゅぎてみえないので、いっぽんのいなじゅまにみえまちゅ…だって。ちゅごいね」 「ん。ちゅごい」 小雪は気分がいつになく高揚しているのを感じた。なんだかすごい秘密を知ってしまった気がした。 「なっちゅ。もっかい」 「うん」 木実はもう一度くりかえした。さっきよりもずっとスラスラ読める気がする。書いてある事は相変わらずよくわからないけれど。 小雪はそれを聞きながら必死に考えた。あったかいとくもができて、つめたくなってこーりができてでんきがおきてかみなりになるんだ。すごい、すごい。誰かがやってるんじゃないんだ。雨とか風とかと同じって書いてあるから、きっといつか止まるんだ。だって雨も風も今まで止まらなかったことないから。本当に良かった。 「よかった」 「よかったの?」 「ん。おんなじ」 とにっこりする。 「おんなじ?なにと?」 木実はもう一度本に目を落とした。なにと同じと書いてあっただろうか?そうか、『あめがふったり、かぜがふいいたりするのと同じしぜんげんしょう』って書いてある。なーんだ、雨とか風といっしょなんだ。誰かが自分達の事を怒ってるわけじゃないんだ。『しぜんげんしょう』って何かわからないけど。 「そっか」 木実も小雪を見てにっこり笑った。 良かった。大事なゆきちゃんが誰かに怒られて怖い思いをしなくてすむ。 雷はまだ鳴っていたけれど、ほのぼのした気持ちで二人は部屋に戻った。どちらからいう事もなく、また二人で窓辺に座り、まだ降っている雨と、少し遠くになった雷鳴を眺めた。 「かみなりきれー」 誰かが怖がらせているのではないと分かったら、木実の目にも急に雷は恐ろしくはないものに見えてきた。 むしろ、小雪と二人で小さな冒険をするきっかけになった大切なもののように目に映る。 「こわくないね」 「ん」 木実は、もういつものように自分を守ってくれようとしている。さっきは怖がっていたみたいだけど。ちょっとだけ勇気がいったけど、行ってみて良かった。いつも自分を大切にしてくれる木実に恩返しができたようで嬉しかった。 「みえないね、おほちちゃま」 「ん」 「あめだからね、ね」 「ね」 「みたいねおほちちゃま」 「みたいね」 「まってゆ?」 「ん。まってゆ」 二人はそっと肩を寄せ合った。 雨は少し弱まってきたようだ。星がいつものように二人に微笑んでくれるのももうすぐだろう。
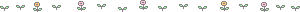
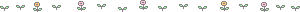
「木実くん、小雪ちゃん」 優しい声に二人は目を覚ました。昨夜はあのまま窓辺のクッションの上で眠ってしまったらしい。 保母がにこにこして二人を見ている。 「昨夜雷鳴ったでしょ。怖くなかった?」 平気と言い掛けて木実はちらりと小雪を見た。小雪は自分が怖がっていたのにきっと気がついていただろう。でももちろん小雪はそんな事は口にしない。 「…あ…」 木実は慌てて起き上がって窓辺に寄った。外はもうすっかり明るくなっている。当然星なんて出ていない。 「おほちちゃま…」 がっかりして小雪の顔を見る。見たかったなお星様。雨上がりの空はきれいなのに。 「お星様?」 保母は笑った。 「二人とも目を閉じて両手を出して」 素直に従う二人の手の平に、何か小さな粒がいくつか置かれた。 「目を開けてご覧なさい」 ドキドキしながら目を開けた二人の目に飛び込んで来たのは 「わあ…」 「おほちちゃま」 手の平の上にお星様みたいに可愛いお菓子がちょこんと乗っていた。 「こんぺいとうよ。食べてごらんなさい」 口に運ぶとほろりと融けて、甘い味が口いっぱいに広がった。思わず頬がほころんでしまう。 「かわいいね」 「かわいい」 二人で揃って 「ありがとう」 と言う姿に保母は目を細めた。本当に素直に育ってくれた。 「じゃ、朝ごはんにするからお着替えしてね」 はーいと返事をしてから木実はそっと小雪に告げた。 「ゆきたん、きのーの、ひみちゅだよ」 小雪は小首を傾げそれからにっこりして頷いた。 これから長い年月をいっしょに暮らして行く事になる、たくさん作るだろうく二人だけの大切な秘密の第一個目。 二人にはまだそんな自覚はないけれども。
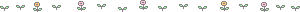
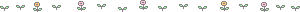
「ゆきたん、もうねる?ごほんよむ?」 時計は7時。まだ寝るのには早い。 「ごほん」 小雪は嬉しそうに答える。 二人は手を繋いで窓際の本棚に向かった。 「これ」 小雪は『ヘンゼルとグレーテル』の絵本を取り出した。最近『白雪姫』の次に気に入っている。 こどもが力を合わせて、大人や悪い魔女に立ち向かうところが好きらしい。 窓辺のクッションに腰を下ろし、二人並んだ膝の上に絵本を開いて木実が読み始めようとした、正にその時だった。 いきなり頭の真上で雷が鳴り響き、部屋の電気が消えた。 「わ…ああああ」 木実は驚いて、絵本を取り落とした。それでも小雪を守らなくてはという一身で両手をぎゅと握る。 「か…かみなりだ…」 「ん」 小雪は手を握り返した。 実はさっきから何か妙な予感めいたものを感じていた。でもそれが何かはわからなかった。今ならば小雪が感じていたのは微妙な気圧の変化で、それは雨と雷の予兆だと説明することができるのだけど。 「ゆ…ゆ…ゆきたん、だいじょおぶだからね。ぼ…ぼくがちゅいてるからね…」 「ん」 真っ暗闇の中で、小雪はこくりと頷いた。 停電に続き、雨がざあざあと音を立てて落ちてきた。それはあたりの音全てをかき消し、まるで世界中に自分達だけしかいないような不安感を煽り立てた。 でも小雪は平気だった。 だって木実がいてくれる。ちゃんと傍にいて手を握っていてくれるから。 もう一度大きな音がして、稲光が部屋を照らした。一瞬目が眩むばかりに部屋が明るくなり、木実は目を閉じてしまったが、小雪はいつもと違う部屋の様子をしっかりと見届けた。 きれいだ、と思った。 いつもよりも濃くなった陰影の中に、家具や出しっぱなしの玩具や木実の顔がくっきりと鮮やかに浮かび上がる。小雪はその光景を頭に刻み付けた。20年の年月を経ても、その時の様子はまるで一枚の絵のように、小雪の記憶にはっきりと残っている。一番古いいくつかの記憶のうちの一つとして。 「なっちゅ?」 黙ってしまった木実にそっと話しかける。 「へーき?」 「う…うん。こ…こわくないよ」 本当は…怖い。 雷なんてどうして鳴るんだろう。空の上で誰かが怒っているとしか思えない。どうしてあんなに怒るんだろう。自分に対して怒っているんだろうか?なんか悪い事をしただろうか。それで大きな音を出して怒りながら罰を与えにくるんだろうか?あんな大きな音を出すんだから、きっとすごく大きくて怖いものに違いない。 そうだ、ゆうべ、寝なさいと言われたのに寝られなくて、遅くまでお喋りをしていたのが分かったんだろうか? それともこの間、食べきれなくてゆきちゃんのの残しかけたお昼ご飯を食べてあげたのがばれたんだろうか? もしかして、お風呂の中でこっそり二人でお湯に潜ってみたのを誰かが見ていたんだろうか? そうだったらどうしよう。罰を受けるのは自分だけではすまないはずだ。 「ゆきたん、ぼくがまもってあげゆからね。ぜったいね」 「ん。あいがと」 「だからゆきたんもこわくないからね」 「ん。こわくない」 「よかった」 小雪のいつもと変わらない落ち着いた声にほっと胸を撫で下ろす。 そうだ、自分はどうなっても、一生懸命謝ってゆきちゃんは許してもらおう。ゆうべ寝られなかったのは自分で、ゆきちゃんは付き合ってくれただけだし、お湯に潜ってみようと言ったのも自分だったし。ゆきちゃんははすごく長く潜れて、ちょっと心配したっけそう言えば。やっぱりゆきちゃんってすごい。 そう思ってほおーっと大きなため息を付いたのと同時にまた大きな雷が鳴った。 「ゆ…ゆきたんっ」 「ん」 二人でぎゅっと抱き合って稲光と雷鳴をやり過ごす。ガラスまでもかたかたと震動するほどの大音響に、思わず身が縮む。 「くらいね」 小雪は部屋の隅に懐中電灯が置いてあるのを思い出した。何かあったら使いなさいと言われた時は、『何か』って何だろうと思ったけれど、きっと今が『何か』に違いない。 「でんき、ある」 「ど…どこに?」 「あっち」 小雪は暗闇の中で、部屋の隅を指差した。 「みえないよ、ゆきたん。みえゆ?」 「ううん」 正確に言えば『見える』わけではない。 でも小雪には暗い中でも物の存在を感じ取れる能力が備わっていた。 「わかゆ」 「わかんの?じゃでんきちゅけられんの?」 「ん」 小雪は立ち上がって懐中電灯をとりに行こうとした。 「まって。いっちょにいく」 木実は手をぎゅっと握りなおし、いっしょに立ち上がった。一人で取り残されたくない、それよりも暗闇に小雪が飲み込まれてしまいそうで不安だった。 どうして他の人が暗闇を気にするのか、小雪にはよく分からなかった。確かにものの形が明確に見えるわけではないので、明るい時と同じに動けるわけではないが。どうも自分以外は、暗闇では物の位置が殆ど分からないらしいと気が付いたのはごくごく最近の事だ。 暗くて歩くのも不安そうな木実を気遣って、ゆっくりと歩く。何分もかけて部屋を横断し、手にした懐中電灯を木実に渡した。木実は渡された小振りの懐中電灯のスイッチを入れた。柔らかい赤っぽい光が二人の回りを照らし、木実はほっと安堵のため息を洩らした。 「よかった」 そう言ってから照れ臭そうに付け加える。 「ごめんね。あいがとね、ゆきたん」 自分が守ってあげるといったのに、助けられてしまった。 ちょっと恥ずかしいけど自分は暗くても困らない小雪が、自分のために灯りのことを思い出してくれたのがうれしい。 木実は片手で懐中電灯を手に持ち、片手で小雪の手を握って慎重にまた窓辺に戻った。まだ雷はひどくて雨も強いけれど、少し明るくなったことで随分気持ちも落ち着いた。 でも、雷が自分達を怒りに来るかもしれないという不安はまだ消えない。 お星様にお願いしようとしても、今夜は全然出ていない。 二人で並んで空を見上げながら 「なんでかな?」 木実が呟いた。 「?」 小雪が不思議そうに木実を見た。 「かみなりなんでかな。なんでなるのかな?なんでぴかぴかするのかな?」 小雪はじっと考えた。 わからない。 自分は雷は怖くない。でもみんなは怖がっているみたいだ。どうして怖いんだろう。いつもはないほどの大きな音と光が出るからだろう。誰があんな事をしているんだろう。誰かが空でしているんだったら、それはとてつもなく大きな力を持った人間が太刀打ちできないような存在に違いない。それにその人がいつまでもそうしたがったら、雷もいつまでも止まらなくて、そうしたら大好きなお散歩もぶらんこもできなくなってしまう。 そんなことを漠然と思う。もちろんちゃんと言葉にしてそんなことを考えたわけではない。ただ、それが不安で不思議に思った。それを知るにはどうしたらいいだろう。そうだ。 「ほん」 「ほん?」 「でてゆ?」 「どっかな?」 木実はいっしょうけんめい考えた。 確かに本は役に立つ。本を見ると字も覚えて、それでまた新しい本が読めるようになる。 「さがす?」 「ん」 それだけしか言わないのに、自分が何をいいたいのかわかってくれる木実をすごいと思う。 他の人は小雪の言いたい事をほとんど分かってくれない。もっとちゃんとお話しなさいと言われるのもしばしばだ。木実だけは一言喋れば言いたい事を理解してくれる。 二人は窓辺の本棚を端から一冊一冊探して行った。 『しらゆきひめ』『あかずきんちゃん』『ももたろう』この辺は明らかに違う気がする。 『おるすばん』『はいきんぐ』これも違う。 『どうぶつえん』『すいぞくかん』ちょっと近づいてきたかな。 『ちきゅうのれきし』『みんなのかがく』あ、この辺かな? 木実は『みんなのかがく』を取り上げた。小雪に懐中電灯を渡して手元を照らしてもらい、ページを繰る。 「わかんないや」 がっかりして本を本棚に戻す。小雪も残念そうにそれを見守った。 「もう、ほん、ないね」 小雪は少し考えてから、ぱっと顔を明るくして言った。 「とちょしちゅ」 「え?とちょしちゅ?」 もっと一般的な本がまとめておいてある通称『図書室』は確かに存在する。しかしそこにはこども二人で行ってはいけないと言われていた。その上、夜なのに暗い廊下を通ってあんな建物の一番奥の方まで行くなんて。二人にとっては立派な冒険だ。 しかし懐中電灯に照らされた小雪の目は真剣で、木実は止めようとは言えなくなってしまった。いつも控えめな小雪だけど、一度言い出すときかなくなる事がある。 「わかった」 木実は頷いた。 「いこ」 「あい」 小雪は嬉しそうに言って立ち上がる。 懐中電灯は木実が持って、しっかりと手を繋ぎなおし、二人は部屋を出た。
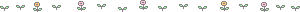
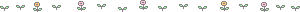
暗い廊下はどこまでも続いているみたいで、木実はおもわずごくりと生唾を飲み込んだ。小雪の手を自分を励ますようにぎゅっと握り、一歩一歩足を進める。 やがてたどりついた図書館も、当然ながら真っ暗だった。 「えと、えと…。どこいく?」 「こども」 「こどものほんのとこ?ん、わかった」 何度かしか来た事はないが、木実はどの辺にどんな本があるかは大体覚えていた。それは木実の能力だった。彼は一度会った人は忘れないし、一度行った場所は決して忘れない。 「このへんだよ」 「そら」 「そらのほん?ん」 木実は端から空に関する本を探し始めた。 『空』という字は知っていた。なぜ『そら』と『空』どっちもあるのかは分からないは。そのどちらもが自分達の頭の上に広がっている青かったり白かったり黒かったりするあの大きなものを指している事は、わかっている。 「これ?」 その中から、『そらのふしぎ』という本を探し出す。表紙にはキレイな青空が広がっている。内容は小学校高学年用のようだった。それを持って二人でテーブルにつく。 小雪は黙ってもくじを見た。 「かみなり」 「かみなり。これだね」 木実は『かみなりの秘密』という文字を探し出した。 「ええと。7と8のぺえじ?」 「7と8のぺえじ」 小雪が繰り返す。 二人は78ページに向けて1ページ1ページ、ページを繰っていった。 書いてある数字のところを見ると、その内容が書いてある事を保母から教わった。保母は二人が理解するか半信半疑だったが、木実は自分のやり方で理解したようだった。つまり数の成り立ちはわからなくて、78ページと26ページのどっちが先かは分からないが、同じ数のところにはとにかくそれが書いてあるというふうに。 「ここ」 「ん。ここ」 二人が見つけ出したページには、今空を走っているのとそっくり同じ稲光の写真が載っていた。顔を見合わせてにっこり笑い、木実はゆっくりと字を追い始めた。 「ん…と…むかちはかみなりを、くもの中にいるかみちゃまや、まものがあばれているものだとおもっていまちた。かがくがはったちゅするにちゅれ、かみなりは、あめがふったり、かぜがふいいたりするのと同じしぜんげんしょうであることがわかってきまちた…。だれかがやってるんじゃないんだ!」 木実はびっくりして小雪を見た。小雪も驚いた顔をしている。 「ぢめんやかいめんちかくのくーきがが、あたたまるとうえにあがります。ちゅるとおんどがちゃがり、ちいちゃいみじゅのちゅぶになります。これがくもでちゅ…くもってみじゅなのっ!?」 「ね」 小雪もますます驚いた表情になる。 という事は、あの不思議な雲みたいなお菓子も水なんだろうか? 「ね。え…と…ちゃらにうえにあがるとおんどがちゃがってこおりのちゅぶになります。それがぶちゅかりあってプラスのでんきがおきまちゅ…。ふう…ゆきたんわかゆ?」 「んーん」 さすがにところどころしかわからない。小雪は素直に首を振った。 ぷらすの電気ってなんだろう??電気って明るくて光ってるのだけじゃないんだ。 「ぼくも。でもよむね。…おもくて、ちたへおちていったこおりはマイナチュのでんきをおこちまちゅ。そのあいだのでんあちゅのちゃが大きくなると、ちょのあいだでほうでんしまちゅ。それがかみなりでちゅ…だって!」 やっとかみなりという言葉が出て来て、木実は良かったとにっこりした。 このままわけの分からない文を読んでいるのはさすがに苦痛だ。 「いなじゅまは、ほうでんげんちょうのひばな、らくらいはほうでんでちゅ。くもと、ちじょうのあいだを、なんどもほうでんをくりかえちてちじょうにちゅきます。しかしにんげんにははやちゅぎてみえないので、いっぽんのいなじゅまにみえまちゅ…だって。ちゅごいね」 「ん。ちゅごい」 小雪は気分がいつになく高揚しているのを感じた。なんだかすごい秘密を知ってしまった気がした。 「なっちゅ。もっかい」 「うん」 木実はもう一度くりかえした。さっきよりもずっとスラスラ読める気がする。書いてある事は相変わらずよくわからないけれど。 小雪はそれを聞きながら必死に考えた。あったかいとくもができて、つめたくなってこーりができてでんきがおきてかみなりになるんだ。すごい、すごい。誰かがやってるんじゃないんだ。雨とか風とかと同じって書いてあるから、きっといつか止まるんだ。だって雨も風も今まで止まらなかったことないから。本当に良かった。 「よかった」 「よかったの?」 「ん。おんなじ」 とにっこりする。 「おんなじ?なにと?」 木実はもう一度本に目を落とした。なにと同じと書いてあっただろうか?そうか、『あめがふったり、かぜがふいいたりするのと同じしぜんげんしょう』って書いてある。なーんだ、雨とか風といっしょなんだ。誰かが自分達の事を怒ってるわけじゃないんだ。『しぜんげんしょう』って何かわからないけど。 「そっか」 木実も小雪を見てにっこり笑った。 良かった。大事なゆきちゃんが誰かに怒られて怖い思いをしなくてすむ。 雷はまだ鳴っていたけれど、ほのぼのした気持ちで二人は部屋に戻った。どちらからいう事もなく、また二人で窓辺に座り、まだ降っている雨と、少し遠くになった雷鳴を眺めた。 「かみなりきれー」 誰かが怖がらせているのではないと分かったら、木実の目にも急に雷は恐ろしくはないものに見えてきた。 むしろ、小雪と二人で小さな冒険をするきっかけになった大切なもののように目に映る。 「こわくないね」 「ん」 木実は、もういつものように自分を守ってくれようとしている。さっきは怖がっていたみたいだけど。ちょっとだけ勇気がいったけど、行ってみて良かった。いつも自分を大切にしてくれる木実に恩返しができたようで嬉しかった。 「みえないね、おほちちゃま」 「ん」 「あめだからね、ね」 「ね」 「みたいねおほちちゃま」 「みたいね」 「まってゆ?」 「ん。まってゆ」 二人はそっと肩を寄せ合った。 雨は少し弱まってきたようだ。星がいつものように二人に微笑んでくれるのももうすぐだろう。
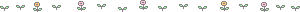
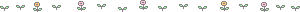
「木実くん、小雪ちゃん」 優しい声に二人は目を覚ました。昨夜はあのまま窓辺のクッションの上で眠ってしまったらしい。 保母がにこにこして二人を見ている。 「昨夜雷鳴ったでしょ。怖くなかった?」 平気と言い掛けて木実はちらりと小雪を見た。小雪は自分が怖がっていたのにきっと気がついていただろう。でももちろん小雪はそんな事は口にしない。 「…あ…」 木実は慌てて起き上がって窓辺に寄った。外はもうすっかり明るくなっている。当然星なんて出ていない。 「おほちちゃま…」 がっかりして小雪の顔を見る。見たかったなお星様。雨上がりの空はきれいなのに。 「お星様?」 保母は笑った。 「二人とも目を閉じて両手を出して」 素直に従う二人の手の平に、何か小さな粒がいくつか置かれた。 「目を開けてご覧なさい」 ドキドキしながら目を開けた二人の目に飛び込んで来たのは 「わあ…」 「おほちちゃま」 手の平の上にお星様みたいに可愛いお菓子がちょこんと乗っていた。 「こんぺいとうよ。食べてごらんなさい」 口に運ぶとほろりと融けて、甘い味が口いっぱいに広がった。思わず頬がほころんでしまう。 「かわいいね」 「かわいい」 二人で揃って 「ありがとう」 と言う姿に保母は目を細めた。本当に素直に育ってくれた。 「じゃ、朝ごはんにするからお着替えしてね」 はーいと返事をしてから木実はそっと小雪に告げた。 「ゆきたん、きのーの、ひみちゅだよ」 小雪は小首を傾げそれからにっこりして頷いた。 これから長い年月をいっしょに暮らして行く事になる、たくさん作るだろうく二人だけの大切な秘密の第一個目。 二人にはまだそんな自覚はないけれども。